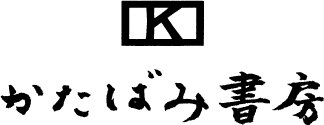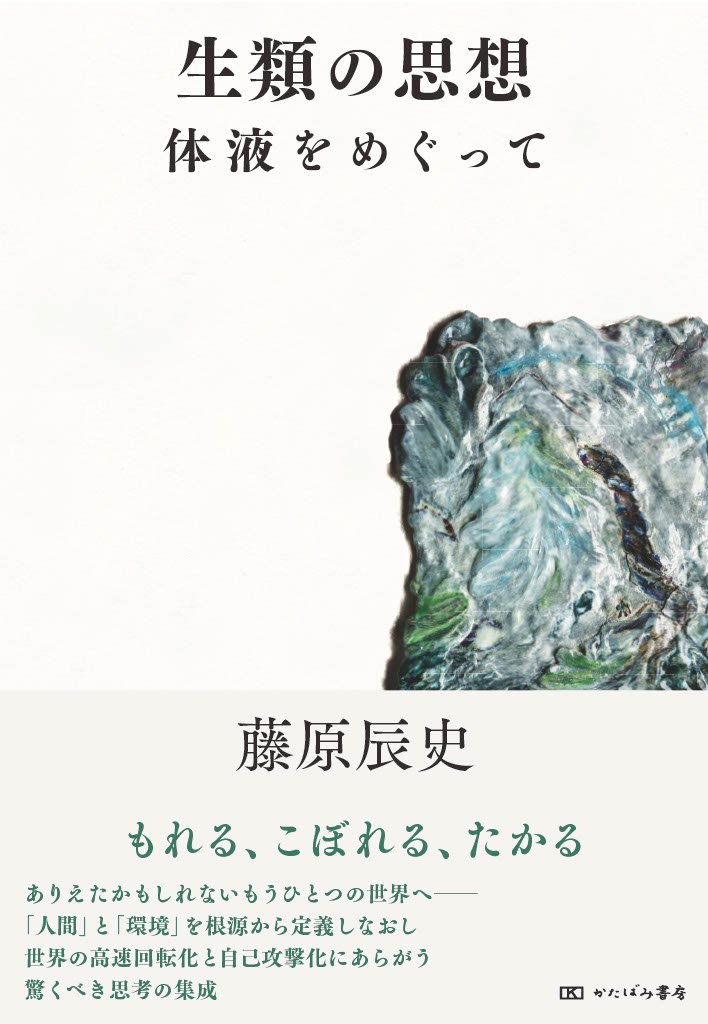
四六判上製288頁
定価:2700円+税
ISBN:978-4-910904-03-0 C0010
装幀:須山悠里
装画:エレナ・トゥタッチコワ
刊行日:2025年10月2日
生類の思想 体液をめぐって
藤原辰史
大気・海洋・土壌汚染、アレルギーの増加、免疫の不調、日常化する暴力、子どもの商品化、奪われる睡眠時間……。この世界の現実をどう捉えるか。
「人間」と「環境」を根源から定義しなおし、ありえたかもしれないもうひとつの世界を描きだす。
世界の高速回転化と自己攻撃化にあらがう、驚くべき思考の集成。
■著者からのメッセージ
人びとを「生き生きとさせないもの」とはなにか——。とくに、この列島を生きる子どもたちをみていると、そんな残酷な問いが頭から離れなくなります。子どもたちを元気づける歌をうたったり、笑わせたりすることが緊急の課題なのかもしれませんが、そんな芸当はもちろん私にはできません。ですからせめて、「生き生きとしている」とはどういうことなのか、それを邪魔しているものはなんなのか、という問いにとことんつきあってみました。本を読んだり、旅をしたり、目をつぶったりしながら考えていると、どうやらこの社会には、「もれる」や「たかる」が足りないのではないか、と思うようになりました。その考えにいたった経緯をこの本にまとめてみましたので、手に取っていただければ幸いです。
藤原辰史
著者について
藤原辰史(ふじはら・たつし)
1976年生まれ。京都大学人文科学研究所教授。専門は農業史、環境史。
著書に『ナチス・ドイツの有機農業』(2005年、柏書房、第1回日本ドイツ学会奨励賞)、『カブラの冬』(2011年、人文書院)、『ナチスのキッチン』(2012年、水声社、のち決定版:2016年、共和国、第1回河合隼雄学芸賞)、『稲の大東亜共栄圏』(2012年、吉川弘文館)、『食べること考えること』(2014年、共和国)、『トラクターの世界史』(2017年、中公新書)、『戦争と農業』(2017年、集英社インターナショナル新書)、『給食の歴史』(2018年、岩波新書、第10回辻静雄食文化賞)、『食べるとはどういうことか』(2019年、農山漁村文化協会)、『分解の哲学』(2019年、青土社、第41回サントリー学芸賞)、『縁食論』(2020年、ミシマ社)、『農の原理の史的研究』(2021年、創元社)、『歴史の屑拾い』(2022年、講談社)、『植物考』(2022年、生きのびるブックス)、『食権力の現代史』(2025年、人文書院)などがある。
目次
はしがき
Ⅰ わずらう
体液をめぐる思考——生類の思想が編み直されるところ
慢性と急性——人文学的省察
「自己する」の不調——アレルギー時代の人文学的考察
Ⅱ あそぶ
家庭科の哲学——「人間する」を遊ぶ
墨色と泥色の記憶——かこさとしの絵の淡い濁りについて
子どもの商品化に抗する思想
いま環境について考えるとはどういうことか
Ⅲ はぐくむ
農業技術への問い——ハイデガーの概念「はぐくむ hegen」について
土の思想をめぐる考察——脱農本主義的なエコロジーのために
さつまいもと帝国日本
賢治と道子をつなぐもの——「植物医師」と硫安
Ⅳ たべる
培養肉についての考察
食の闇について
人間チューブ論——食のダイナミズムを考える
エディブル・プラネット
Ⅴ まじる
「規則正しいレイプ」と地球の危機
表皮の脱領域的考察
もれる——膜が食い破られること
「たかり」の思想——食と性の分解論
あとがき
初出一覧
人名索引
書評情報
![]() 湯澤規子(人文地理学、法政大学教授)
湯澤規子(人文地理学、法政大学教授)
- 東京自由大学webマガジン「なぎさ」
「台所文芸論 生と死をめぐる食卓」第4回
「生と死が交歓するぬか床 梨木香歩『沼地のある森を抜けて』
https://nagisamagazine.wixsite.com/t-jiyudaigaku/news/categories/湯澤規子
![]() 小林えみ(マルジナリア書店店主、よはく舎代表)
小林えみ(マルジナリア書店店主、よはく舎代表)
- 本チャンネル 2025年12月28日
「本屋店主たちが語る 2025年ベストブック!」
https://www.youtube.com/watch?v=-9DTkngtogg
![]() 諏訪敦(画家、武蔵野美術大学教授)
諏訪敦(画家、武蔵野美術大学教授)
- 芸術新潮 2026年1月号
「環境と身体、考察が混じり合うところ」
![]() 天ぷらそば食べよ(河出スタッフ)
天ぷらそば食べよ(河出スタッフ)
- Web河出「なんでこの傑作がうちの本じゃないの⁈」本読み河出スタッフが選んだ今年のベスト本2025年版
「思考するって、こういうこと!」
https://web.kawade.co.jp/column/174975
![]() 植田将暉(早稲田大学大学院法学研究科、ゲンロン編集部)
植田将暉(早稲田大学大学院法学研究科、ゲンロン編集部)
- 「今週の人文ウォッチ#55」2025年の人文書徹底レビュー
https://www.youtube.com/watch?v=5AYndKEvSyQ (1:52:30〜)
![]() 四方田犬彦(比較文学・映画誌)
四方田犬彦(比較文学・映画誌)
- 「2025年下半期読書アンケート」
図書新聞 3716号(2025年12月20日)
![]() 福嶋聡(書店員)
福嶋聡(書店員)
- 書標(丸善ジュンク堂書店) 12月号
![]() 雑賀恵子(農学言論/社会思想)
雑賀恵子(農学言論/社会思想)
- 「「当然」の世界の在りようを揺るがせる——環境の代わりに「生類」ということばを基盤に据え生存に対する暴力について考える」
図書新聞 3715号(2025年12月13日)